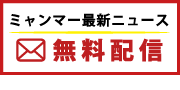このコラムは、ミャンマー在住の日本人ジャーナリストが『日刊ベリタ』に匿名で寄せたものをMYANMAR JAPONが固有名詞や用語を本誌に合わせて再編集したものです。記事の内容は筆者の見解であり、弊社ならびに日刊ベリタの意見を表すものではありません。
スマホと銃、反軍武装闘争で躍動する「Z世代」
ミャンマー最前線からのレポート(6)
西部チン州の山岳地帯と平野部のマグウェ管区での取材で、筆者は各地の反軍武装勢力間の相互連絡や協力態勢に注目した。目にしたのは民主派の国民統一政府(NUG)との提携も進み、ミャンマー軍を「戦略的防御」に追い込んでいく光景である。それと、この共闘推進にクーデター後の市民不服従運動(CDM)に参加したZ世代の若者が欠かせない役割を果たしている姿である。最新の通信技術と武器を駆使して躍動する彼らに出会った。
▽「文民統制」めざし新たな行政機構が始動
2021年2月のクーデター後に反軍武装闘争が開始されてから間もなく、軍・警察及び関係者に対する「報復」「行き過ぎた攻撃」のほか、時には「私刑」「虐殺」も行われ、「内ゲバ」も発生したと伝えられた。もともと暴力行為すべてに拒否反応が強い日本国民の間では、すっかりミャンマー民主化闘争への支援は途絶してしまった。
現在、その問題が解決しつつあるのか、それとも深刻化しているのか。筆者は現地で確認したいと思っていた。結論からいえば、相当程度その行き過ぎは是正され、自制が利いて理性的な対応がひろがっていた。
クーデター後、最初に武装闘争を開始したチンランド防衛隊(CDF)か活動する地区では、新たな行政機構をつくり警察や法廷制度を住民の意見を聞きながら創設し、コメ生産や野菜栽培、家畜、石油、ガソリン、バイクなどの車両、教育、幼児、病院などなど細かい部門を担当する委員を決めていた。
その部門のひとつに軍事があり、将来的には「文民統制」を実現しようとの意図が感じられた。村からミャンマー軍に加わる、あるいは援助する人がいても、「制裁」行動は禁じられ、話し合いと説得により解決しようとしている。
そのCDF組織にヨー市民防衛隊(YDF)のメンバーが訪問し、談笑しているシーンを目撃した。彼はマグウェ管区のYDF本拠地から7時間ほどバイクを走らせて来たといい、自動小銃を携行していた。カメラを向けると、上気しながら説明してくれた。「ヨー族は、おもにチン州の山からマグウェの平野部にかけて住む少数民族なのだが、稲作や上座部仏教、風俗習慣などはほとんど全てビルマ族と同一で、なぜ我々が少数民族とされているのか分からないくらいだ」と語った。YDFは現在では500名の戦闘員を擁し、8割のヨー民族から支持されているという。
交渉の結果、CDFとYDFの戦闘員が筆者の警備兼案内役を務め、古い四輪駆動車でマグウェ管区まで連れていってくれることになった。
車を7時間近く走らせ、5か所のCDFやYDFの検問を抜けマグウェ管区に入り、平野部では各町村のPDF(市民防衛隊)の検問所を10か所ほど通った。どの検問所にも武装した隊員が駐屯し、道路を行き来するバイクや車両、通行人をチェックしている。薄暗くなっても目立つ武装車両、所属組織のバッチや肩章を確かめると、そのまま通行を許可し不審や警戒の姿勢はなかった。各武装組織の相互連絡や協力態勢がかなり整ってきたことを伺わせた。
チン州と接したザカイン管区の要衝タイゲーン攻略作戦には4つの武装組織が合同作戦を展開し、ミャンマー軍は敗走した。軍は空から報復の爆撃を実行し、タイゲーン市を廃墟にしてしまった。
武装勢力間の対立抗争に関する話は聞かなくなっている。もちろん完全に火種が消えたとはいえないだろう。チン州のなかでもチン国民軍(CAN)チン族軍とCDFの確執はいまだにある。創設1988年のCANと政治組織チン民族戦線(CNF)はチン族を代表する組織としてCDFを傘下に収めたい。一方、CDFはクーデター後真っ先に決起し、大きな成果を挙げ行政面でも先進をゆく自負があり、「CANはミャンマー軍との和平を追求するなど優柔不断だった」とみていた。
この種の軍と戦闘するか和平を重視するかの路線の相違は、多くの少数民族武装組織のなかにもある。あるいはあったと言ったほうがよさそうだ。
クーデター以降、軍に妥協せず戦闘で活路を切り開くという潮流が支配的となった。カレン族の武装組織の例はその典型だろう。1949年以来の「世界最長の内戦歴」をもつカレン民族同盟(KNU)とその軍事部門カレン民族解放軍(KNLA)は、ミャンマー軍との和平協定を破棄して軍との戦闘を強化した。また、長年「軍の別動隊」だった民主カレン仏教徒軍(DKBA) は、昨年8月に軍から離れKNUと共同歩調をとることを決めた。そして、この数か月連戦連敗だった軍がDKBAにソーウイン准上級大将(軍ナンバー2)を派遣し、「軍側に戻ってくれ」と説得したが、失敗に終わったという。(「The Irrawaddy」2024年1月25日)
こうして少数民族武装組織がこぞって反軍の戦線を築いたことは、都市部と平野部のPDFを大いに鼓舞し、この間進めてきた各種の矛盾と部分対立を解消する取り組みに力を与えている。
▽「やむなき抵抗」から「勝ち戦」へ
2021年までは、この種の矛盾も伝えられた。軍の弾圧に抗しようと、まずは少数民族武装勢力の地域に保護を求め、武装訓練を受ける都市部の若者が増えた。訓練を終えた彼らは、武装闘争に加わるため地元に帰りたいだが武器が無い。「面倒」をみた武装組織は「いま帰っても力にならないだろう。武器を与えるからここで我々の戦力になってくれ」とリクルート工作もなされる。
その反対の例もあった。NUGはPDFを立ち上げたものの、圧倒的に経験ある戦士がいない。そこで、少数民族の兵士をリクルートしようとする。「3年契約で働いてくれないか」「長すぎる、1年でどうだ」「給料や待遇はどうなるのか」こうしたやりとりもあった。ミャンマー軍からの手あたり次第の武力弾圧が広まるにつれ、各地に自発的な反軍の武装集団がつくられた。「NUGは掛け声だけで当てにならない」との不満もひろがった。この時期は確かに軍警関係者への「報復行為」はあった。
筆者はその時期にヤンゴンの工科大出身者らからなる「銃器製造秘密工場」をタイ・ミャンマー国境で取材したことがある。米国から支援にきた若者が中心となり、ミャンマーのエンジニア志望の青年らが昼夜製造作業に取り組んでいた。その中心メンバーの父親は軍の将校だった。父親は薄々気づいているだろうが、息子のことが明るみに出るとクビになるか逮捕されかねないと黙ってくれているという。それにしても、やむにやまれぬ気持ちは分かるが「絶望的な抵抗」のように感じたのも確かだ。
それから2年余、事態は大きく変わった。びっくりするほど多くの場所で銃器、兵器の製造がおこなわれているのを知った。Siyinの民兵組織の指揮官は「我々は既にロケット砲の実射訓練を終え戦闘に使用できるところまできた」と語った。「負け戦」覚悟のやむなき抵抗ではなく、「勝ち戦」が見えてきたというのだ。
その推進力をZ世代が担っていることを各地、各場面で目撃した。CDM(市民不服従運動)や軍の弾圧への抵抗の時期に、10代~20代の青年層がSNSやスマートフォンの撮影機能を使い運動を組織化していったことは良く知られている。その延長で、武装闘争や反軍民主勢力同士の連絡、協力、共闘などの活動においてもアンテナとなり、コーディネーターとなって活躍している。スマホと銃を自由に扱うZ世代にミャンマー軍は頭を抱えているにちがいない。
他勢力のメンバーともすぐに仲良くなり、シグナル(Signal)はじめ安全度が高いとされるメッセンジャーアプリを使い(ミャンマーでLINEを使用する人は少ない)、情報交換もテキストだけではなく映像を送り合う。必要とあらば、武装組織間の連絡を取り持ち、共闘を実現させる。その行動力には目をみはるものがある。
チン州の山岳地帯の村でも通信タワーがそびえているのを目にすることがあった。インターネット機能を駆使する反軍若者世代に大苦戦しているのになぜ軍はその通信ネットワークをつぶさないのだろう、筆者の素朴な疑問に対して彼らはあっけらかんと答えた。「軍は金欠状態、スマホビジネスの収益は絶対失いたくないはずだ」
軍を「戦略的防御」に追い込んだいまZ世代は、よりのびのびと動き回っているのである。明らかな事実は、CDMに加わったその世代が、とりわけ先進的な役割を果たした若者の圧倒的部分が武装闘争断固支持となっているということである。
我々3名の取材班の移動には、多い時には6台のバイクが使われた。そのドライバーの1人は元ツアーガイドだった。実家がバイク修理屋をやっていたが、その技術がなかった彼は外国人のツアーガイドとしてバイクで山々を案内して回った。そして、クーデター後はすぐにCDMのデモに参加した。熱心に参加し腕に Spring Revolution(春の革命)と入れ墨まで入れた。が、警察にそれを見られたら捕まると思い、それならばいっそ武装闘争を支援しようと決心したと語った。
現在、彼はCDFの情報収集、運搬役になっている。元公務員だったバイクドライバーは「ミンダッ市では数千人がCDMに合流したが、そのうち90%は武装闘争に参加するか支持している」と答えた。
筆者が目にした現実は、ミャンマー西部の山岳地帯とマグウェ管区の一部である。だが、ザカイン管区やラカイン州、シャン州でもミャンマー軍は敗走を続けている。すでに国土の優に6割は軍の支配が及ばなくなりつつある。 (つづく)
© Berita
バックナンバー
(1)ミャンマー軍の崩壊が始まった
(2)独裁者は孤立し疑心暗鬼に
(3)スー・チー氏復権の可能性も
(4)軍高官や軍政支持者からもミン・アウン・フラインに辞職要求の声
(5)「史上最悪のリーダー」はいかにして生まれたのか