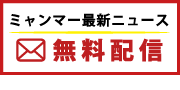このコラムは、ミャンマー在住の日本人ジャーナリストが『日刊ベリタ』に匿名で寄せたものをMYANMAR JAPONが固有名詞や用語を本誌に合わせて再編集したものです。記事の内容は筆者の見解であり、弊社ならびに日刊ベリタの意見を表すものではありません。
ミャンマー軍の崩壊が始まった
ミャンマー最前線からのレポート(1)
筆者はこのほど、ミャンマーの西部山岳地帯を中心に延べ二千数百kmを移動し、各地でミャンマー軍が前線から敗退、戦線離脱、反軍勢力側に保護を求め、なかには反対組織の戦闘員となっている兵士の存在も確認した。2021年2月1日にクーデターで権力の座に就いたミャンマー軍は、それから3年目にして崩壊しはじめている。
▽チン州の反軍武装組織キャンプ
インド国境に接するチン州で、軍のクーデター後いち早く武装闘争を開始したチンランド防衛隊(CDF、ミンダッ)の司令官と会談した。34歳の司令官は「決起した時は戦闘員60名だけだった」と言い、決起場所を案内してくれた。深いジャングルに造られた軍事キャンプには現在二十数名の兵士(内3名は女性)がいるだけで、多くは前線に派遣されているとのことだった。
そのキャンプには、意外なことにガンジーやアインシュタインの肖像画と「、他人がいやがることをすべきではない。自分がいやなことを他人にはさせないでいたい(ガンジー)」、「自分と異なるひとたちには感謝すべきだ。それゆえに自己が存在できる(アインシュタイン)」などの言葉が掲げられていた。
キャンプ内の戦闘員らはみな若く、初めての外国からの訪問客に緊張しはにかんでいた。若竹のような率直さがあった。チン族というと、文献資料からは「狩猟民」だが「クリスチャン」でもあるといったイメージがまず浮かぶ。その程度だ。我々の浅薄な知識を恥じ、現に目前にいるチン族の老若男女の精神の成り立ちと構造をなぞってみたいという欲求にかられる思いだった。
一般に日本人のビルマ観、ミャンマー観はまるっきしズレているのではないか。そのズレはどこからきているのだろうか。「日本人に似ていて親しみがもてる。敬虔な仏教徒でコメに生きている穏やかな国民。親日国」といった受け止め方が大半だろう。筆者はそれに全く同調できない。むしろアジア諸国のなかでも最も理解しにくい国であり国民であると常々思っている。
ミャンマーは大小135の民族から成る多民族国家であり、1948年の建国以来76年間内戦状態が絶えたことがない。国土の4割以上、人口の3分の1を少数民族が占め、英国の植民地支配を124年間受け、軍事独裁政治が半世紀以上にわたる(1962~2011年、2021~24年)。 憲法がなかった時期が32年間(1962~74年、1988~2008年)、全国の大学閉鎖が10年以上ある国だ。
この歴史の重荷のなかで暮らしてきた民衆の精神、心情がどのようなものであるか、そして国のあり方や権力、政治への姿勢がどのようなものであるか。我々は自分たちの尺度は全く通用しないことを出発点としなければならない。
今回の旅でこういう質問を受けた。親日家を自負する30代の女性である。「私たちがやむを得ず、当然の権利として武装闘争を始めたら、日本からの支援の声がピタっと止んでしまった。私たちにはどうしても理解できません。軍は本来外国から攻めてきたときに国を守る役割があった筈です。それが軍と警察が無防備な我々を情け容赦なしに殺してくる。私たちはもはや、人間の尊厳、生命保持の権利として武器を取ったのです。もしも、日本の自衛隊や警察が圧政に反対する国民に空爆、砲撃、狙い撃ち、無差別殺戮をやってきたら、日本の皆さんはどうするのでしょうか」
▽市民防衛隊の自主管理下の村
クーデターから3年という節目がやってくるが、最初に武装決起をしたミンダッ地区のCDFがどうなっているのか。そして「苦戦」が伝えられているミャンマー軍の現状はどうなのか。反軍の民主勢力にとって、今後の展望は開けるのか。そこを知りたいと思い難行ともいえる旅にいどんだのだった。
中国製の古い125ccバイクの後ろに跨り、カメラと寝袋を持ち、険しいでこぼこ道を5日間移動の強行軍だった。同行者からは「安全には最大限気を付けますが、空襲や砲撃があれば、命の保障はできません」とも言われていた。
マグウェ管区に入ったときは、民主勢力の市民防衛隊(PDF)がダムと水力発電所の軍駐屯地を攻略し、自主管理を開始していた。周辺の村落には真夜中でも電気がいきわたり、最大都市ヤンゴンの停電事情とは打って変わった光景を見た。
その周辺で一泊したとき、同行のミャンマー人スタッフ(元政治囚)は密かに己にこう言い聞かせていたという。「軍が報復作戦をしかけてくるだろう。そのときは武器をもって戦う覚悟をしていた」。「彼(筆者のこと)は日本人だから捕まったとしても殺されることはないだろうが、自分は政治囚だったから殺される。それならまだ戦って死ぬ方がいい」
その地域のPDF戦闘員らは、軍の空爆を警戒しながら深夜も大勢集結し、血気盛んにお互いに檄を掛け合っていた。
だが、ミャンマー軍兵士はやってこなかった。ここだけでなく二千数百キロ移動しても1人も見なかった。戦闘地域の駐屯地、キャンプ、詰所、検問所から敗走し、拠点基地に集結しそこに立て籠っている。かつて50万余の兵力(警察軍含め)を持つ一大勢力で、どこにいても眼を光らせていた暴力装置はウソのように消えていた。
マグウェPDFのたまり場ともなっている食堂では、住民らがミャンマー将棋の賭けに興じている。村のおばあちゃんは「軍隊がいなくなって安らいでいるよ」と言い、ヤンゴンの日本語学校通っている青年は「久しぶりにバスを乗り継いで帰ってきたけど村はやっぱりいい。まだ危険はあるけどね」と語った。
少数民族武装勢力内部の紛争、抗争、自発的に各地で武装闘争を開始した平野部のPDFの軍警関係者への「制裁処刑行為」はどうなっているのか。これを現地で確かめたいということも、取材の重要な目的であった。 (つづく)
© Berita